日本の伝統文化の一つ茶の湯(茶道)は鎌倉時代に始まり安土桃山時代、いわゆる戦国時代に大成しました。
安土桃山時代に活躍し茶の湯を大成させた茶人といえば千利休です。
千利休は織田信長、そして豊臣秀吉と時の権力者の庇護のもと茶道を大成させます。
なぜ安土桃山時代に千利休は茶の湯が大成することができたのか?
そこには織田信長や豊臣秀吉の政治的な思惑が絡んでいます。
戦国時代の日本では茶の湯に用いられる「茶器」の価値が暴騰しており、城や領土並みの価値がありました。
(現代でも戦国時代の茶器には億単位の値段が付くそうです。)
この茶器の価値付けを行っていたのが千利休です。
当時茶人として名声を帯びていた千利休が「価値がある」と言うだけで陶器や磁器で出来た茶器が一国と同等の価値に化けていくのです。
もちろんこの価値付けを裏で指示していたのは織田信長や豊臣秀吉です。二人はどんな思惑で利休にこのようなことをさせたのでしょうか。
織田信長が天下統一に向けて快進撃を続けていました。彼は尾張(現在の愛知県西部)から全方位に戦線を拡大していきます。
しかし戦を続けていくうえで困ったことがありました。配下の武将たちに対する恩賞の問題です。
当時の恩賞は主に領地で、配下の武将が戦で活躍すると土地を分け与える形で配っていました。
最初は問題が無かった恩賞問題も天下統一に近づくにつれて戦は増えるが、分け与える土地が不足するという悪循環に陥ります。
困った織田信長は堺の商人の間で流行っていた茶の湯に目を付けます。
織田信長は茶の湯を格式高い儀式として扱い、その茶の湯で使われる茶器を恩賞とする形で上記の問題を解決しました。
配下の武将には茶器を恩賞として与え、またその茶器を使った茶会を開く権利を与えました。
茶会を開く権利を「御茶湯御政道」といいました。
この解決策は上手くハマり戦国武将達は恩賞として与えられる茶器に夢中になり、それを使う茶の湯にも夢中になっていくのです。
そしていつしか茶器は所有しているだけで権力の象徴になっていきました。
この後も茶の湯と政治はどんどん結びつきが強固になり、織田信長の死後は豊臣秀吉に引き継がれる形で発展していくことになりました。
[編集後記]
それにしても茶器のような器が一国と同じ価値を持つなんて、今では考えられませんよね。
現代で例えると都道府県の全土地が茶器と同じ価値があるってことですから。
でもこれって僕らが1万円札に対して思い込んでいることと同じなんですよね。

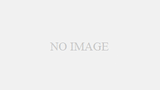
コメント